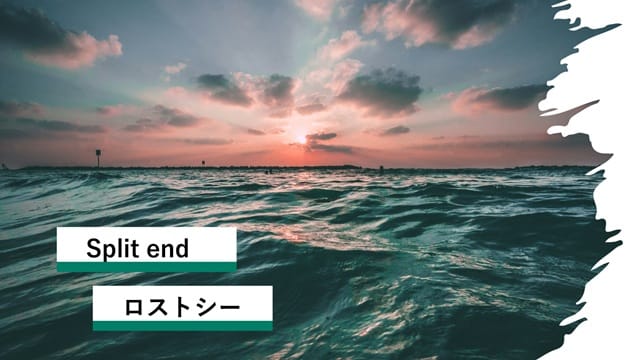
迷いと希望が交差する、現代の青春ロック──Split end「ロストシー」ライナーノーツ
みなさんこんばんは。音文学を毎日書いているとあっという間に休日も終わってしまいました。明日からまた平日が始まりますが、そんな2025年のひと夏の休日が終わるライナーノーツはSplit endの「ロストシー」という楽曲を紹介していきます。
ちなみに前回の記事では、パソコン音楽クラブの隠れた名曲「KICK & GO feat.林青空」を紹介しました。是非併せてご覧ください。記事はこちらから。
目次
はじめに:新世代のギターロックの旗手、Split endとは
奈良県発のバンド、Split endは透き通るようなボーカルと、エモーショナルなギターフレーズ、そして詩的な言葉選びで注目を集めてきました。彼女たちの楽曲は、単なる青春ではありません。痛みやもどかしさ、誰にも言えない感情までもを包み込み、そっと背中を押す力を持っていると考えています。
そんな彼女らの代表曲と言っても過言ではないのが「ロストシー」です。2016年のリリース以降、リスナーの間でじわじわと支持を集め、ロストシーは圧倒的なクオリティのライブを行う彼女たちのバンドの核をなす楽曲へと成長していきました。
本記事では「ロストシー」の音楽的構造や歌詞の世界観、バンドの背景と共にその魅力を深堀りしていきたいとおもいます。
「ロストシー」が描く”迷い”と”確信”
感情を引き裂く、イントロのギターとリズム
「ロストシー」は、印象的なクリーンのギターフレーズから幕を開けていきます。リバーブのかかったその響きは、まるで海の深淵に沈み込むような感覚すら覚えさせます。すぐにバンド全体が入って来るが、その音像はあくまで繊細で、音の「余白」がしっかりと保たれています。
ドラムとベースは非常にタイトです。BPM自体は速すぎず、むしろミディアムテンポぐらいではありますが、ギターのメロディーとボーカルのラインが絶えず動き続けることで、楽曲全体に”前に進んでいる感覚”が宿っています。
個人的に思うSplit endの特徴でもある「静けさの中にあるエモーション」が、この冒頭だけでしっかりと提示されているのではないでしょうか。
抱えきれない不安、それでも海に出る覚悟
歌詞の主題は、タイトルの通り「失われた海」=ロストシーだと思います。だが、この”海”は物理的なものではないと考えられます。すなわち”自分の可能性”や”未来への希望”が失われてしまった状態を指しているのではないでしょうか。
海がみえるここで さよならをした
海が枯れる頃に 君に会いに行く
引用:AWA(こちら)
と歌われる冒頭では、人生という大海原の中で漂流するような、ままならなさが感じられます。しかし、この「君に会いに行く」があることで、完全に絶望しているわけではない事も分かります。しかし、海が枯れる頃というのは現実に起きる事ではないとも読み取れるので、「君に会いに行く」日は来ないかもしれないとも捉えらえます。
この両義性が「ロストシー」の持つ魅力の一つだと思われます。つまり、”迷っているのに、どこかで希望を信じている。”その感情が、Split endのサウンドとボーカルでより一層リアルに伝わって来ると思われます。
Split endの音楽的アプローチ:ポストロックとJ-POPの美しい交錯
美しくも緻密なギターアレンジ
Split endのギターアンサンブルは、シンプルに聴こえて実は非常に凝っています。「ロストシー」は多重録音で2本のギターが巧みに分業しており、片方は主旋律をなぞるリード的な役割、もう片方はコードやアルペジオで空間を埋めています。
特にサビに入る前のブレイクは、声だけになる。そこにギターのコードもベースのルート音もなにもない。この”不安定なコードが存在しない感覚”が、まさに「海がみえるここで さよならをした」という歌詞のテーマとリンクしており、演奏そのものが感情表現になっていることが分かる。
サビで爆発するエモーション
面白い手法だと思っているのですが、サビの歌詞はイントロと全く同じもののリフレインになっています。イントロでインパクトのある歌詞を置いてそれをサビでもリフレインする事で、歌詞の意味や感情をより一層強める効果があると考えられます。
この特徴を最大限活かせるポテンシャルを持っているのがSplit endというバンドの強みだと考えられます。”叫びのような透明感”がここにはあります。心の叫びは叫んでいても、音は決して荒くはなりません。むしろ、全てのサウンドが繊細に設計されており、ノイズではなく「感情の震え」として表現されていると考えられます。
歌詞に託された青春の「境界線」
「君」と「僕」の関係性
「ロストシー」の歌詞には、度々「君」が登場する。この「君」は、特定の誰かを示しているようでいて、実は”過去の自分”や”人生像”とも読めるような存在だと考えます。
君が僕を愛して
いたかどうかなんてさ
明々白々なくらい簡単な話
引用:AWA(こちら)
という歌詞は、誰かとの思い出を反芻しているようでもあるし、自分が追い求めた夢の痕跡を振り返っているようにも読めます。切なさもあれば、どこか急激なリアリティもあります。色んな「含み」を持った歌詞で秀逸だなと思いました。
現在地を探す旅の途中
”ロストシー=失われた海”という比喩は、最後まで一貫しています。しかし、物語の終盤で歌われる以下の一節に注目してみましょう。
海が見えるここで
さよならをさよならを
引用:AWA(こちら)
ここに至っては、歌の語り手は”失われた海”に絶望するのではなく「見えない未来」と「過去」への決別をすると見せかけて断言をしていないのです。さよならを”した”かどうかは歌詞に込められていない。そこにはリスナーの想像力を試しているような実験的な事をしています。それが、「ロストシー」という楽曲の本当のコアになる部分かなと思っています。
終わりに:ロックバンドという灯台、Split endの現在地
Split endが「ロストシー」で示したのは、迷いと葛藤の中でも決して歌うことを辞めない姿勢であと思います。煌びやかなサウンドや派手な演出ではなく、丁寧に紡がれた言葉と音で、”聴く人の孤独”に寄り添おうとしています。
それはまるで、夜の海に差し込む一筋の光のようでもあります。決して全体を照らし出すことはできないかもしれません。けれど、その光に導かれて誰かが”進みだす”きっかけになるのなら、バンドの存在意義はそこにあるんだと思います。
「ロストシー」はSplit endの静かながらも確かな決意を音にした一曲だと思います。そして、迷いながら生きる全ての人にとって”新しい航路”となるのではないでしょうか。

音文学管理人。TSUJIMOTO FAMILY GROUP主宰。トラックメイカーでもありながら、音文学にて文学的に音楽を分析している。年間数万分を音楽鑑賞に費やし、生粋の音楽好きである。また、辻本恭介名義で小説を執筆しており処女作「私が愛した人は秘密に満ちていました。」大反響を呼び、TSUJIMOTO FAMILY GROUPの前身団体とも言えるスタジオ辻本を旗揚げするまでに至っている。




