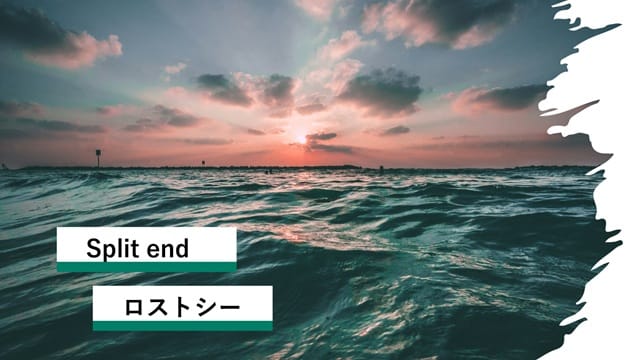出会いと別れ。そういった感情をストレートに描きぬいた名曲──osage「ウーロンハイと春に」徹底解説
皆さんこんばんは。音文学管理人の池ちゃんです。連日猛暑が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。執筆しているお部屋は常時エアコンをフル稼働させております。寝苦しい日々が続いておりますが、皆様お体ご自愛下さい。
さて、今回は季節は違いますが春っぽい楽曲のご紹介です。この楽曲は私が何気なくSpotifyで音楽を聴いていた時に偶然おすすめに出てきて聴いたものとなります。私の心をストレートに貫いた楽曲で是非とも紹介したいなと思い、今回紹介させて頂きます。それでは本文スタートです。
ちなみに、前回の記事はSplit endさんで「ロストシー」を取り上げています。併せてお読みいただければと思います。記事はこちらから。
目次
はじめに──osageの魅力と「ウーロンハイと春に」の位置づけ
osage(オサゲ)は、瑞々しい感性と文学的な詞世界、そしてギターを中心としたオルタナティブ・ロックサウンドを特徴とする、日本の若手ロックバンドです。そのサウンドは、どこか懐かしさを帯びながらも、現代の都市に生きる若者の「心なき心情」を代弁してくれるような、優しくも鋭い力を持っています。
そんなosageの代表曲のひとつが「ウーロンハイと春に」です。本作は色々な解釈があるかと思いますが、音文学的には恋愛の終わりとその後に訪れる再生の予感を描きながら、喪失と希望が同居する季節──「春」という時間の流れの中で、聴き手をしっとりと包み込みます。日常的なモチーフを通して、普遍的な感情を浮かび上がらせるこの曲はosageの作家性が強く表れた楽曲だと思われます。
osageが描く日常と詩情──タイトルに込められた意味
「ウーロンハイ」が象徴するもの
「ウーロンハイと春に」というタイトルは、非常にユニークで象徴的な意味が込められていると思います。まず皆さんも目に入ってきたのは「ウーロンハイ」という単語です。ウーロンハイは、若者が気軽に飲むお酒として広く親しまれていますが、この曲においては単なる飲み物以上の役割を果たしていると考えられます。しかしながら、面白い事にウーロンハイという言葉は歌の中では一回しか出ません。
変わらない街並みの中で
変われないで残された
あの店のウーロンハイが濃いめだった
嫌いにはなれなかった
引用元:AWA(こちら)
この一区間でウーロンハイが出てきますが、楽曲中ではかなり印象的なメロディーラインなので、ここの一回だけでも印象深く聞き取れます。個人的な考察にはなりますが、別れの痛みや孤独をアルコールで和らげるといった描写でしょうか。そういった意味では「ウーロンハイ」は一種の慰めであり、感情を薄める道具として登場しているのではないでしょうか。
「春」がもたらす再生の予感
「春」という季節は、日本人にとっては特別な意味を持ちます。卒業や入学、出会いと別れ──そうした移ろいが集中的に起こる季節です。「春に」と題されるこの楽曲では、過ぎ去った関係への哀愁と、それでも前へ進もうとする小さな決意が同時に歌われています。つまり、「ウーロンハイ」と「春」は過去と未来、痛みと希望を象徴する両極として並べられていると考えられます。
osageの歌詞に見る情景描写と感情の揺らぎ
等身大の感情と都市の空気感
歌詞全体を通して感じられるのは、日常の中に潜む詩情です。
見慣れない街に背を向けて 駆け上がった改札口
急行電車の通過待ち 二番線から強い風が吹いて
引用元:AWA(こちら)
上記の様な描写は、誰もが一度は体験したことのあるような場面でありながら、特定の誰かの記憶に深く根差しているようでもあります。都市の空気、夜の寒さ、人混みの中の孤独感、そうした都市生活の機微が、osageの柔らかい言葉で丁寧に描かれていると言えます。
意外にも「あなた」という言葉が少ない
この楽曲の最大の特徴とも言えるのが「あなた」という言葉が少ないという事です。歌詞の至るところで別れを匂わせる描写があるのに、具体的に相手を指す言葉が極端に少ないのです。この存在しない「あなた」はすでに過去の存在であり、再び戻ることのない関係を語っているのではないでしょうか。それでも、歌い手は「あなた」との日々を反芻し、アルコールの力を借りながらその影に寄り添おうとしていると考えると胸がキュっとなります。この曖昧で揺らぐ距離感が、楽曲全体に一貫した切なさを与えています。
サウンドの構成と感情の演出
控え目で繊細なアレンジ
「ウーロンハイと春に」のサウンド面は、決して派手ではありません。むしろ控え目で、ギターのアルペジオやシンプルなコード感が空間をそっと満たすようなアレンジが特徴的です。その静かな響きの中に、歌い手の内面が浮かび上がるような構成がとられています。
ドラムやベースも極端に前に出ることはなく、リズムは淡々としながらも温度を感じさせるプレイがなされています。これは、感情の大波ではなく、じんわりと染み入るような「余韻の情景」を大切にしているからこそのアプローチだと考えられます。
「ウーロンハイと春に」におけるクライマックスの抑制
多くのポップスでは、サビやアウトロで感情が爆発し、カタルシスを与えるような演出がなされますが、「ウーロンハイと春に」ではあえてその「爆発」を避け、感情の高ぶりそらも穏やかに描かれています。ラストのサビ部分はドラムのキックが4つ打ちになりますが、それ以外の変化はありません。歌詞には変化はありますが、楽器隊の変化は控え目となっています。この抑制された構成が、楽曲全体のリアリティや誠実さを生み出しており、osageらしい音楽的信念が感じられます。
おわりに──osageの音楽が描く「わたしたちの物語」
「ウーロンハイと春に」は、決して大声で感情を叫ぶような楽曲ではありません。しかし、その分聴き手一人一人に「あなた自身の物語」を投影させる余白を持っています。誰もが経験するかもしれない「ささやかな別れ」や「心の整理」、そして「前へ進む覚悟」が、この楽曲には静かに、でも確実に息づいています。
osageの音楽は、感情の過剰な演出よりも、感情の「手触り」に寄り添うことを大切にしていると考えられます。その姿勢は「ウーロンハイと春に」おいて特に顕著であり、だからこそこの楽曲は、春の空気にそっと混ざり込むようにして、私たちの日常のか片隅で鳴り続けてくれるのではないでしょうか。

音文学管理人。TSUJIMOTO FAMILY GROUP主宰。トラックメイカーでもありながら、音文学にて文学的に音楽を分析している。年間数万分を音楽鑑賞に費やし、生粋の音楽好きである。また、辻本恭介名義で小説を執筆しており処女作「私が愛した人は秘密に満ちていました。」大反響を呼び、TSUJIMOTO FAMILY GROUPの前身団体とも言えるスタジオ辻本を旗揚げするまでに至っている。