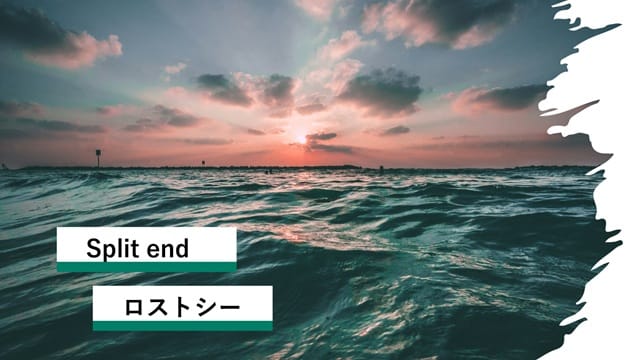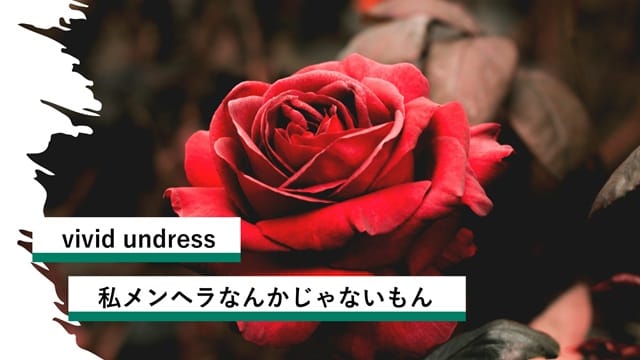
【徹底解説】vivid undress「私メンヘラなんかじゃないもん」に込められた歌詞の意味と音楽的魅力
皆さんこんにちは。今日も音文学の時間がやってまいりました。今日で音文学ができて7カ月目という事であっという間の約半年でした。これからも時間をみつけて音文学の方を更新していきますので、何卒宜しくお願いいたします。
さて、今回はvivid undressさんで「私メンヘラなんかじゃないもん」を紹介していこうと思います。vivid undressさんは私が学生時代の頃によく聴いていたバンドだったので、個人的にはずっと紹介したかったバンドになります。それではいきましょう。
ちなみに前回はなきごとさんで「メトロポリタン」を紹介しました。宜しければ併せてご覧下さい。記事はこちらから。
目次
vivid undressと「私メンヘラなんかじゃないもん」という楽曲の位置づけ
vivid undressは、ポップスのキャッチーさとロックのエネルギー、さらにジャズやプログレッシブな要素も融合させた独自の音楽性で注目を集めてきたバンドだと言えます。そのサウンドは技巧的でありながら聴きやすく、また歌詞の世界観も鋭い切り口とユーモアを持ち合わせていると言えます。
「私メンヘラなんかじゃないもん」は、そんなバンドの個性を強く打ち出した一曲です。タイトルからして挑発的でありながらも、聴き進めるうちに深いメッセージ性を持っていることに気づかされます。この楽曲は単なるキャッチーなフレーズの羅列ではなく、現代社会における「心の在り方」と「自己意識」を鋭く描写した楽曲だといえるでしょう。
タイトルが示す挑発とユーモア
「メンヘラ」という言葉は、ネットスラングとし広まり、多くの場合ネガティブなニュアンスを含んで使われます。しかし、この曲のタイトルはその言葉を逆手に取り、「そんなラベルを貼られたくない」「私はもっと自由に存在していい」という強い自己主張を感じさせます。これは私の一考えですが、この思考こそvivid undressのスタンスと重なって、リスナーに「固定観念を壊す」メッセージを届けているのかなと思います。
歌詞に込められたメッセージ
「私メンヘラなんかじゃないもん」というフレーズは、単に自己否定をしているのではなく、他者から押し付けられるレッテルを拒否する姿勢として受け取ることもできます。
他者の視線と自己肯定
私メンヘラなんかじゃないもん
この世界で生きていきたいもん
ただ世知辛いとは思ってんもん
だってだってだって神様が
与えた性格が難題で
足りない頭をフル回転して苦労してんだもん
引用元:Uta-Net(こちら)
このような歌詞を見て楽曲全体から通じて浮かび上がるのは、「他社の評価に縛られながらも、自分を肯定したい」という葛藤です。歌詞の中では、一見自虐的な表現や弱さの吐露が散りばめられていますが、それは決して敗北宣言ではありません。むしろ「弱さを認めても、私は私」という強さへと転じていきます。
自分の弱さを肯定するという強さ
現代の音楽シーンにおいて、自己肯定をテーマにした楽曲は数多くあります。しかし、この曲は「弱さ」や「不安定さ」を真正面から扱いながらも、それを恥じるのではなく「そういう自分も含めて肯定する」という立場をとっています。この視点が、聴き手に強烈な共感を呼び起こしていると考えられます。
サウンドとアレンジの魅力
この楽曲の大きな特徴は、その音楽的アプローチにあります。vivid underssならではのアレンジが、歌詞のテーマをさらに際立たせています。
ポップとロックの融合
楽曲はポップスの軽快さを持ちながらも、ギターリフやリズムセクションにはロックの力強さが感じられます。イントロからリスナーを惹き込み、サビに至るまでの展開は非常にドラマチックだと思います。この緩急のある構成が、歌詞の中で描かれる感情の揺れと見事にリンクしていると思います。
ボーカル表現のダイナミズム
ボーカルの表現力も、この楽曲の大きな魅力です。繊細に吐き出される弱音、そして力強く響くサビのフレーズ。そのコントラストが、歌詞の持つ「揺れる心」と「抗う強さ」を余すことなく表現していると思います。聴いているとまるで主人公の心の動きを追体験しているかのように感じられるでしょう。
リズムの軽快さと複雑さ
リズムアレンジには、ポップに聴かせつつも複雑なニュアンスが含まれています。これはvivid undressが持つ「聴きやすさと技巧の両立」の象徴ともいえる部分で、音楽ファンから高い評価を受けているのではないかと考えられます。
「私メンヘラなんかじゃないもん」が与える影響
リスナーに響く共感性
この曲は単なるキャッチ―な楽曲にとどまらず、聴く人それぞれが抱える「見られ方」と「自分らしさ」という普遍的なテーマに触れています。特に、SNS時代において「他者の目」にさらされる事が日常になった若い世代にとって、この歌詞の持つ意味は非常にリアルで、共感を呼びやすいと考えられます。
バンドの存在感を確立する楽曲
また、この楽曲はvivid undressというバンドの音楽的な個性を広く知らしめた一曲でもあります。独自の言葉選び、緻密なサウンドアレンジ、そして社会性を帯びたテーマ。それらすべてが詰め込まれており、バンドを代表する楽曲としてリスナーの記憶に刻まれていると思います。
まとめ
「私メンヘラなんかじゃないもん」は、挑発的でユーモラスなタイトルの裏に、深いメッセージと音楽的な完成度を兼ね揃えた名曲です。他者から押し付けられるラベルを拒否し、弱さを抱えたまま自己を肯定する強さ。その姿勢は、現代を生きる多くの人々に響き、励ましになっているのではないでしょうか。
vivid undressが放つこの楽曲は、聴き手に「自分を認めることの大切さ」を教えてくれると同時に、バンドの音楽的冒険心と表現力を体現する一曲といえると思います。

音文学管理人。TSUJIMOTO FAMILY GROUP主宰。トラックメイカーでもありながら、音文学にて文学的に音楽を分析している。年間数万分を音楽鑑賞に費やし、生粋の音楽好きである。また、辻本恭介名義で小説を執筆しており処女作「私が愛した人は秘密に満ちていました。」大反響を呼び、TSUJIMOTO FAMILY GROUPの前身団体とも言えるスタジオ辻本を旗揚げするまでに至っている。